「栗(くり)」は、イガに包まれた木の実で、秋の味覚として日本でも広く親しまれています。甘栗、栗ご飯、モンブランなど、菓子や料理にも欠かせない食材です。
世界でも栗は食文化に取り入れられており、国ごとに独自の呼び方があります。
この記事では、様々な国と文化で使われる「栗」の表現をご紹介します。
- 世界の『栗』の表現を一挙紹介します
- 食文化と結びついた栗の呼び方も分かります
世界各国の「栗」の表現まとめ
日本語:栗(くり)
日本語の「栗(くり)」は、ブナ科クリ属の木の実を指します。栗ご飯や甘栗など、古くから秋の味覚として愛されています。
英語:chestnut(チェスナット)
英語では「chestnut」が栗を意味します。「roasted chestnuts(焼き栗)」は冬の風物詩としても有名です。
中国語:栗子(リーズ)
中国語では「栗子(lìzi/リーズ)」と呼ばれます。特に「糖炒栗子(táng chǎo lìzi/甘栗)」は中国の街頭で人気の食べ物です。
韓国語:밤(パム)
韓国語では「밤(bam/パム)」が栗を意味します。韓国料理にも多く登場し、栗入りの餅や薬菓などに使われます。
フランス語:châtaigne(シャテーニュ) / marron(マロン)
フランス語では「châtaigne(一般的な栗)」と「marron(大粒の食用栗)」の2種類の言葉があります。モンブランの「マロン」はここから来ています。
スペイン語:castaña(カスターニャ)
スペイン語では「castaña(カスターニャ)」と呼ばれます。秋の市場で売られる焼き栗は「castañas asadas」として親しまれています。
ドイツ語:Kastanie(カスターニエ) / Esskastanie(エスカスターニエ)
ドイツ語では「Kastanie(栗の木、栗の実全般)」が基本です。食用の栗は特に「Esskastanie(食用栗)」と呼ばれます。
イタリア語:castagna(カスターニャ) / marrone(マッローネ)
イタリア語では「castagna(栗)」が一般的ですが、大粒の栗を「marrone」と呼びます。イタリアのお菓子「マロングラッセ」にも使われます。
ロシア語:каштан(カシュタン)
ロシア語では「каштан(kashtan/カシュタン)」と呼ばれます。木を指す場合にも同じ単語が使われます。
アラビア語:كستناء(カスタナー)
アラビア語では「كستناء(kastanāʼ/カスタナー)」が栗を意味します。市場や屋台で焼き栗が売られるのは中東でも冬の風物詩です。
ヘブライ語:ערמון(アルモン)
ヘブライ語では「ערמון(armon/アルモン)」と呼ばれます。イスラエルでも輸入された栗が秋冬に出回ります。
タイ語:เกาลัด(カオラット)
タイ語では「เกาลัด(kao-lat/カオラット)」と呼ばれます。中国の影響で炒り栗(炒เกาลัด)が広く食べられています。
最後に
この記事では、世界各国の言語での「栗」の表現をご紹介しました。
「chestnut」「栗子」「밤」「castaña」など、栗は世界各地で親しまれる食材であり、文化的にも季節の象徴として位置づけられています。
各国語の呼び方を知ることで、「栗」という言葉に込められた食文化や季節感をより豊かに味わえるでしょう。
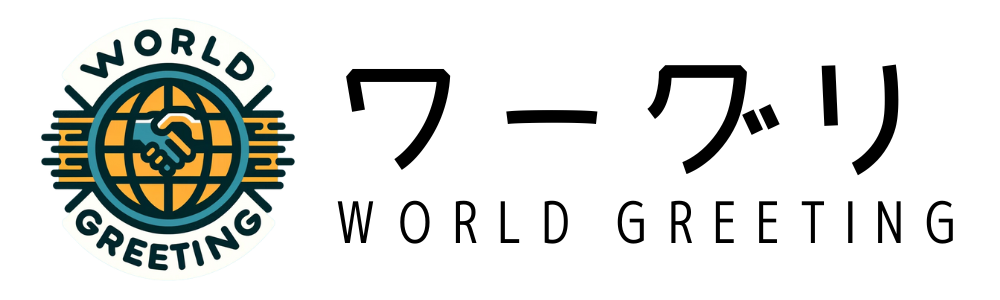
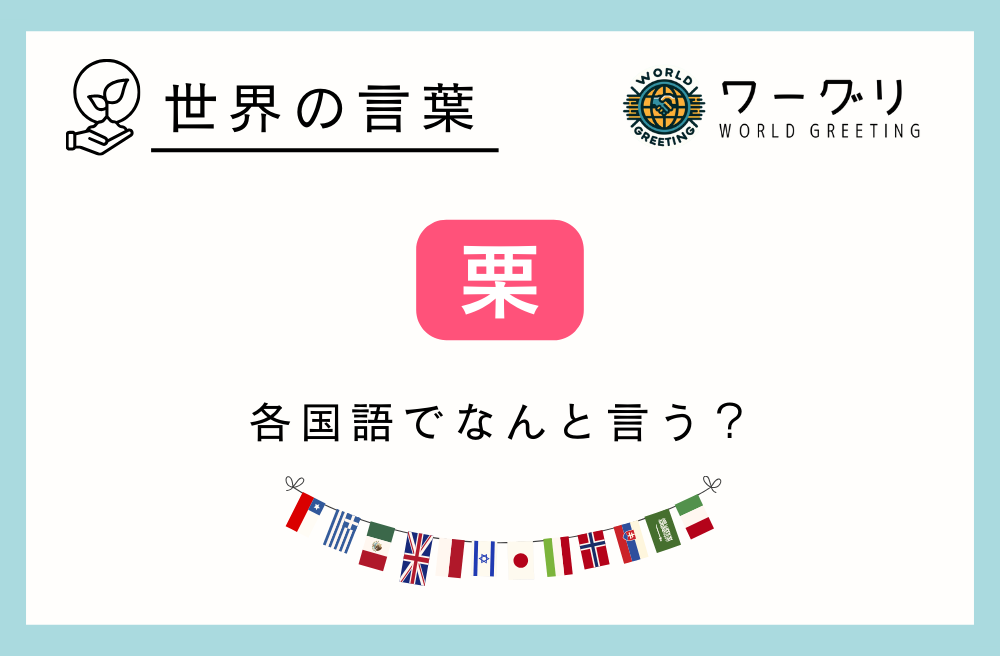

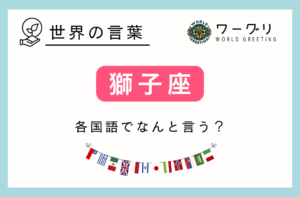
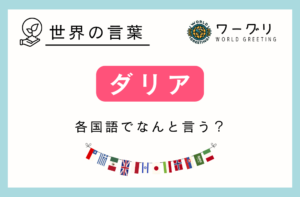
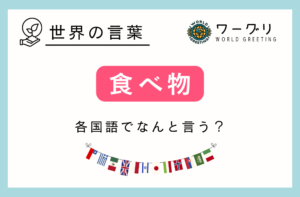
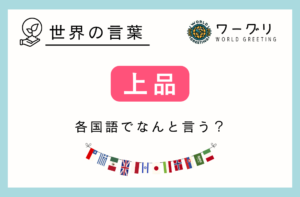
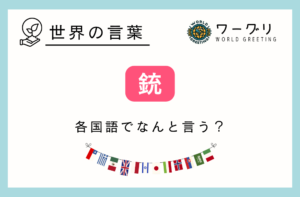
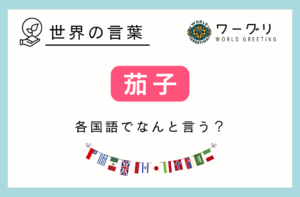
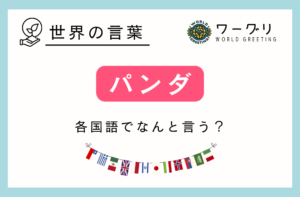
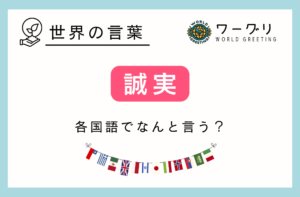
コメント