「狐(きつね)」は、日本や世界の神話・民話に登場する動物で、知恵・変化・狡猾さ・神秘性の象徴とされます。日本では稲荷神の使いとして神聖視され、中国や西洋でも物語に多く登場します。
この記事では、各国語における「狐」の表現をまとめました。
世界各国の「狐」の表現まとめ
日本語:狐(きつね)
日本語の「狐(きつね)」は、稲荷神の使いとして神聖な存在とされる一方で、妖怪や化け狐としても語られる多面性を持っています。
英語:fox(フォックス) / vixen(ヴィクセン)
英語では「fox(フォックス)」が一般的です。特に雌の狐は「vixen(ヴィクセン)」と呼ばれ、転じて気の強い女性を表す比喩にもなります。
中国語:狐狸(フーリー) / 狐(フー)
中国語では「狐狸(húlí/フーリー)」が最も一般的です。簡略形で「狐(hú/フー)」とも言い、妖艶さやずる賢さの象徴として民話に多く登場します。
韓国語:여우(ヨウ)
韓国語では「여우(yeou/ヨウ)」と呼びます。伝承の「九尾狐(구미호/クミホ)」は妖しく美しい女性に化ける狐として有名です。
フランス語:renard(ルナール) / renarde(ルナルド)
フランス語では「renard(ルナール)」が雄雌共通の一般的な呼称です。雌を特に指す場合は「renarde(ルナルド)」が使われます。寓話『ルナール物語』でも有名です。
スペイン語:zorro(ソロ) / zorra(ソラ)
スペイン語では「zorro(ソロ)」が雄の狐、「zorra(ソラ)」が雌の狐を指します。「怪傑ゾロ」の名前にも使われており、ずる賢さや俊敏さの象徴です。
ドイツ語:Fuchs(フックス)
ドイツ語の「Fuchs(フックス)」は狐を意味し、姓や地名にも使われます。賢さや狡猾さを表す比喩としても用いられます。
イタリア語:volpe(ヴォルペ)
イタリア語では「volpe(ヴォルペ)」と呼ばれます。寓話や文学ではずる賢さの象徴として多く描かれます。
ロシア語:лиса(リサ) / лисица(リシーツァ)
ロシア語では「лиса(lisa/リサ)」が一般的に雌狐を指し、「лисица(lisitsa/リシーツァ)」も広く使われます。雄を特に言う場合は「лис(lis/リス)」です。
アラビア語:ثعلب(サァラブ)
アラビア語では「ثعلب(tha‘lab/サァラブ)」が狐を意味します。寓話や比喩の中で「狡猾さ」を象徴します。
ヘブライ語:שועל(シュアル)
ヘブライ語では「שועל(shu‘al/シュアル)」と呼ばれ、聖書にも登場します。多くの場合ずる賢さの象徴です。
タイ語:สุนัขจิ้งจอก(スナック ジンジョーク) / จิ้งจอก(ジンジョーク)
タイ語では正式に「สุนัขจิ้งจอก(sunak jingjok/スナック ジンジョーク/狐犬)」といいますが、短縮して「จิ้งจอก(jingjok/ジンジョーク)」とも呼ばれます。
ポルトガル語:raposa(ハポーザ)
ポルトガル語では「raposa(ハポーザ)」が一般的な表現で、文学作品や寓話にもよく登場します。
ヒンディー語:लोमड़ी(ローマディー)
ヒンディー語では「लोमड़ी(lomṛī/ローマディー)」と呼ばれ、インドの昔話やことわざにも頻出する動物です。
インドネシア語:rubah(ルバ)
インドネシア語では「rubah(ルバ)」が狐を意味します。スラングとして「ずる賢い人」を指すこともあります。
ベトナム語:cáo(カオ)
ベトナム語では「cáo(カオ)」が狐を意味します。「con cáo(コン カオ)」と冠詞をつけて動物名として使います。
トルコ語:tilki(ティルキ)
トルコ語では「tilki(ティルキ)」と呼びます。ずる賢さや計略の象徴としてことわざにも多く登場します。
ペルシャ語:روباه(ルーバーフ)
ペルシャ語では「روباه(rūbāh/ルーバーフ)」と呼ばれ、イランの民話や寓話でずる賢い動物として登場します。
最後に
この記事では、世界各国の言語での「狐」の表現をご紹介しました。「fox」「renard」「zorro」「Fuchs」「volpe」「лиса」「raposa」「tilki」など、どの言語でも知恵や狡猾さの象徴として語られます。
ネーミングや創作に活かす際には、それぞれの言語が持つ神話的・文化的な背景を踏まえると、より独自性のある表現が生まれるでしょう。
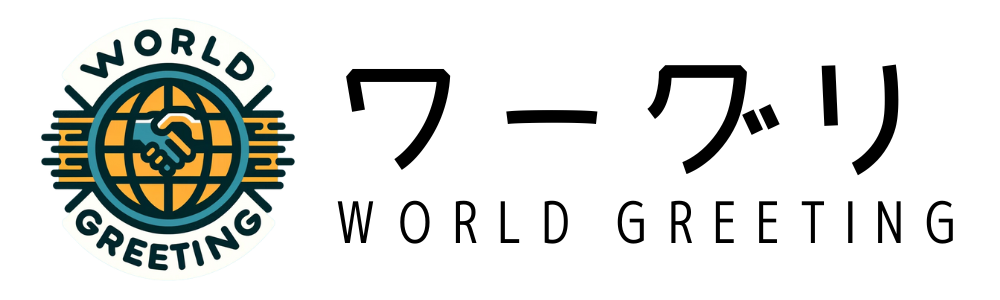
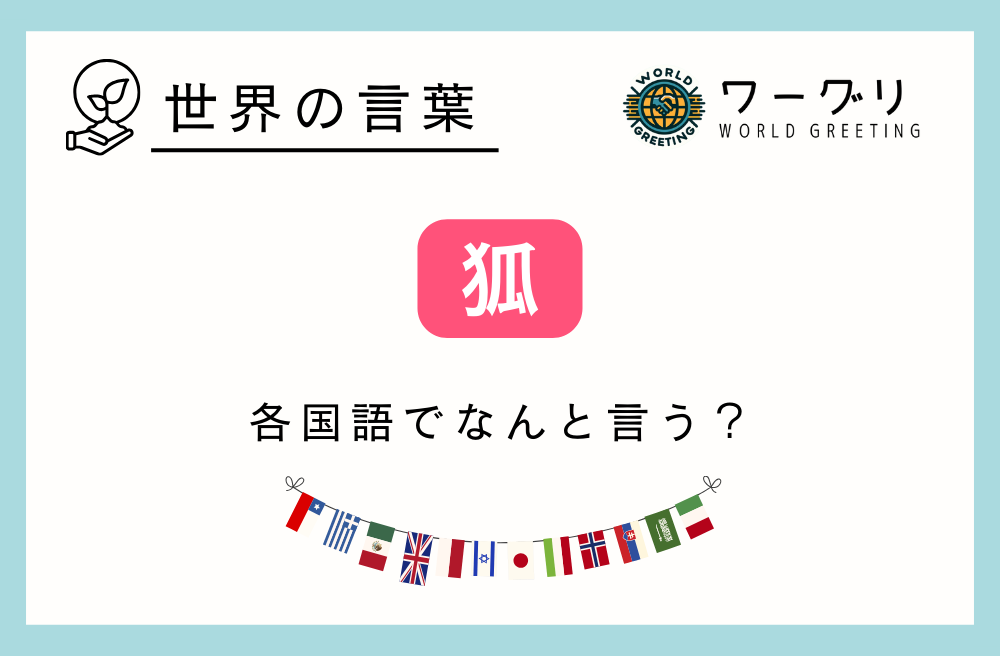

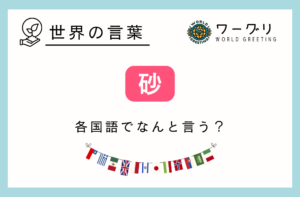
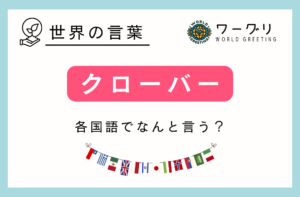
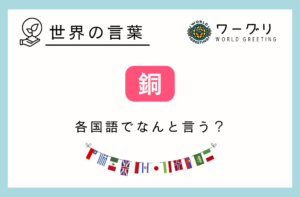
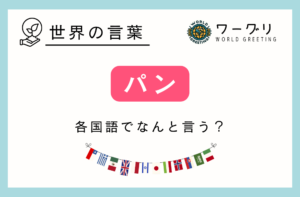
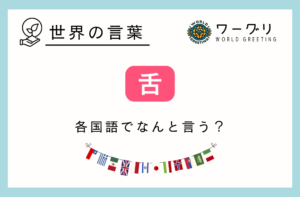

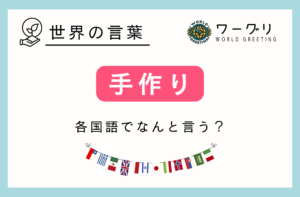

コメント